1週間ほど温泉地へ旅に出ていた。
雄大な自然と美味い飯、暖かな土地の人々との交流に心が洗われるようだった。
しかし長旅を終えて新宿駅に降り立った時、その空気に心底ほっとしたのもまた事実だ。
雲を見下ろす神々しい山の山頂よりも、歌舞伎町のストゼロ臭い腐った空気が俺には合うらしい。
東京は、新宿は、俺のような人間すべての故郷である。
実際のところ俺は千葉県の片田舎出身だが、もはや人生の半分を東京で過ごしてしまったし、千葉は「行く」ところであり、東京は「帰る」場所と無意識に呼んでいる。
人間にとって故郷とは、帰るべき場所とはどこなのか。
今回はそんなセンチな気分に浸る夜、読みたい1冊をご紹介する。
綺麗事なしで、ただそっと寄り添う『夜のことばたち』
整形、パパ活、ホス狂い、風俗、夜職、SNS依存……。もはや聞き飽きたことばたちだ。
どれだけテレビやネットで偉い学者の先生や政治家やアナウンサーがそれらの「闇」を問題視したところで、東京・新宿を故郷に持つ我々には何ひとつ響かない。
ダイアナ著『夜のことばたち』は、学者や政治家の言う「現代の闇」とやらを日常として生きる、たくさんの女性たちの物語だ。
美しさや承認欲求やホストに貢ぐため、彼女たちはパパと寝るし、夜の街で心や体も切り売りする。
そのことにほんのわずかな罪悪感や苦悩も感じながら、しかし彼女たちから悲痛さのようなものは感じられない。
そんなもの東京という街では日常であり、生活であり、身近であり、そういう文化圏を生きているというだけにすぎない。
「郷にいれば郷に従え」という言葉通り、嫌なら田舎でのんびり暮らせばいいだけだ。
わざわざ規格外に高額な家賃を払って東京に住んでいるのには、やはりそれなりの価値や意味があるからである。
だが時々、「本当の自分」みたいなものがわからなくなるのもまた東京の持つ強烈な魔力の作用だと言える。
都会を自分の生きる場所として選んだことに後悔はないけれど、時々胸に去来する「あれっ……?」というわずかな違和感。
自分はここで何しているんだろう。何が欲しかったんだろう。
そんな女性たちの抱く小さな迷いや哀しみを、ベタベタとした味付けで重ったるくすることなく、シンプルに飄々と描いている、オムニバス形式の作品だ。
「現代の闇」なんていう安っぽい言葉で枠にはめたり、片付けたりしない。
同時に、媚びて必要以上に歩み寄ったりもしない。ただそっと距離を取りつつ、そばにいる。そんな作者の視線には、清々しさすらある。
そう、それはまるで俺が愛した「東京」という街そのもののような在り方だ。
東京という街はいつも雨が降っているような気がする
新宿2丁目で夜職をしていた頃、東京という街はいつも雨が降っているみたいだなと思っていた。
薄暗くて冷たい。誰もがいつも見えない傘を差していて、それで自分の顔を覆い隠しているようだ。
すけべな客に尻を揉まれている時も、行きずりの男とラブホテルで寝ている時も、駅前でお巡りさんに職質を受けている時も、目の前の人々が傘よりこっち側に決して踏み込んでこない。ひとりぼっちを生きている感じがした。田舎育ちの俺には、それが心地よかった。
この本の中に、俺のお気に入りの短い話がある。
梅雨の季節、低気圧による頭痛と生理痛が重なってしまった女性は1人で苦しんでいる。
誰もいないベッドで1人体を横たえながら、過去の辛い出来事を思い返したり、普段なら気にかけないような些細なことにも傷ついている。
ロキソニンが効いてきた彼女は毛布にくるまり、ようやく安らかな眠りにつくことができる。
涙を流しながら、その瞬間彼女は思う。雨の音を聞きながら毛布にくるまって眠ると胎内にいた時を思い出す気がする、と。
衝撃的な描写も、話題性のあるテーマでもない短い話だが、これは東京(都会)という土地の心地よさを、とても美しく描いているように思う。
誰もが個人主義で、一線を踏み越えてこない東京という街。マンションの隣の部屋にどんな人が住んでいるかなんて、知らないという場合がほとんどだ。
それを冷たいという言い方もできるが、他者に侵されない領域を持って生きることができるのは、安らかでもある。
俺の生まれた土地ではそれは叶わなかった。
ゲイであること、夜職をしていたこと、長男なのに独身であること、かつて奥さんのいる人を死ぬほど好きになったこと、今はケチな物書きをしていること、自分の顔が嫌いでそろそろ整形に手を出したいと考えていること……。
その全てがあの土地にいれば許されなかっただろう。
別に田舎の慣習を否定する気はない。ただ俺には合わなかった。
あの土地にいる限り俺は「ニセモノの人生」を生きねばならなかった。
だから東京に逃げてきたのだ。本当の自分を求めて。
皮肉な話だ。何もかもが作り物の東京という街で、唯一見つけたのが「本当の自分」「本物の人生」だったとは。
だが生まれた土地を捨て、高い家賃を払う価値は、間違いなくあった。
東京は冷たいけれど優しい。俺がどんな生き方をしても、放っておいてくれるから。
この漫画の作者もそうだ。女性たちに寄り添った作品ではあるが、彼女たちを変えようとか、救おうなんてことは思っていないように見える。
ただ放っておいてくれる。そのなんと心地よいことか。優しいことか。
帰るべき故郷とはどこだろうか?
帰るべき故郷とは何か?それは己の魂が安らかでいられる場所であるべきだ。
瞼を二重にしたり、顎を削ったくらいで息がしやすくなるなら、それを許してくれる場所を故郷と呼んでも構わないじゃないか。
生まれたまま、ありのままの姿を本当の自分だと思う必要はない。生まれた土地や、血縁や、過去をルーツだと思う必要もない。そんなものに囚われて生きるのは、若さの無駄遣いだ。
キャバやホストで働く人々は、生まれ故郷への愛や関心が薄いように見えることが多い。
夜職をするのはもちろん金のためでもあるだろうが、どこかで過去の自分を捨てたい、別人になりたいという願望があるのではないだろうか。
そしてそれを容易く叶えてくれるのが、東京という街だ。
なんにせよ自分で気に入った最適解な自分こそ、本当の自分であり、ありのままの自分だ。
「あの頃」の自分は別に嫌いでいい。田舎で干し芋を齧っていた頃のダサい自分が許せないならそれは本当の自分じゃないし、居場所でもない。
自分を定義していいのはいつだって自分だけだ。他人ではない。
新宿2丁目で酔い潰れたり、マッチングアプリで一夜のお相手を見つけたり、堂々と男と手を繋いで街を歩けるのが本当の俺であり、それを許してくれるのが俺の故郷である東京だ。帰るべき場所は、ここにある。
だけど人は弱いから、迷ったり、どうしようもなく寂しくなったりする夜もある。
世界中で自分がひとりぼっちみたいな気分になるそんな夜は、夜風に吹かれながらそっとこの本を開くといい。
「ひとりじゃないよ」なんてこの本は言わない。
ただそういう夜を過ごしているのは、何もあなただけじゃないという「ことばたち」で満ちている。それで充分じゃないか。







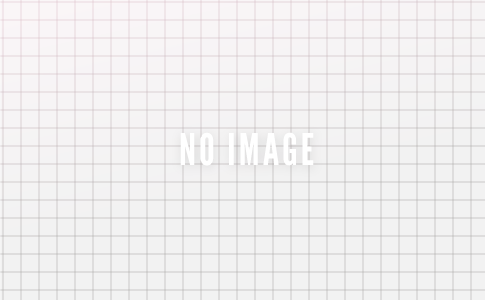










![.
💛夜職デビュー!ナイトワーク初心者向けの業界ガイド💛
ナイトワークをしてみたいけどよくわからない…という方に向けて、どういった風にナイトワークを探していけばいいか、わかりやすいガイドを書いてみました。初心者でわけもわからずになんとなくスマホでポチポチ~っと検索したら出てきたお店に入って「思ったのじゃなかった…」と失敗、なんて残念なことにならないように。まずは下準備をしてみることから始めましょう!
1️⃣ナイトワークの選び方!自分の働き方を見つけるには?
夜のお仕事というと札束!ドレス!スーツ!キラキラ輝く世界!かけひき!
…というイメージがありますが、まぁあながち間違ってはいません。それはさておき。まずは夜職選びの際に決めることは「本業」とするのか「副業・アルバイト」として働いていくのかで大きく変わってきます。
[ナイトワークを副業とする際の注意点]
まず本職が副業OKなのかどうかの確認が必須です。本業の少し足しにしたくて始めたのに、バレて本業がクビになってしまっては本末転倒!!それからたとえ副業がOKの会社だったとしても「ナイトワークで働く社員がいる」ということは、会社のイメージを損なうからという理由で本業にペナルティを追う場合もあります。
副業として行う場合、ナイトワークがバレないように気を付けるることにとにかく気を配ってください!地域を考慮することや、同僚や上司にバレにくい会員制の高級なお店にするなど、対策を考えておくことが大切です。
ただ、会員制のお店で社長とエンカウント!という可能性もあるので、バレにくい地域にするのが適策ですね。本職の会社からなるべく離れた地域をおすすめします。飲みに来た上司軍団に囲まれて逃げ場が無くなるなんてこともあり得ます。
自分の通える範囲でナイトワークがある地域、バレにくい穴場探しをしてみましょう。
[ナイトワークを本業とする際のお店探し]
ナイトワーク一本で働いていく場合、自分に合っている仕事がどういったものなのかやどれくらい月に稼げるかをしっかりと調べる必要があります。時間帯なども、生活リズムを変えていけるのか、日中働いていきたいのか。そういったことにも注目してみてください。
ナイトワークと一言で言っても細かく色々なジャンルがあります。
◯水商売
キャバクラ、クラブ、ガールズバー、ラウンジ、コンパニオンなど
◯風俗
デリバリーヘルス、ソープ、性感エステなど
◯その他ナイトワーク
メンズエステ、チャットレディなど。
男性も同じです!男性のナイトワークと言えばホストが有名ですがメンズバー、メンズパブ、女性用風俗など色々な働き方法がありますよ!
まずはこの大きなジャンルの中から自分が働いてみたいジャンルは何か決めましょう。
[体験入店をうまく利用しよう!]
ナイトワークでは通称「体入」という一日体験入店が出来るお店がほとんどです。お店によっては何度か体入できるお店も。
自分がどういう仕事が合ってるのかわからない場合、色々なジャンルのお店で一日体験として働いて決めてみるといいでしょう。もちろん、体験入店だけでもお給料はしっかりもらえるので安心してくださいね!
ナイトワークの体入はお店の求人サイトや、直接電話やLINEなどをして決めることが出来ます。「人が足りてないから今日すぐに来て!!」と言われることも珍しくないので、心の準備をしておきましょう。
2️⃣ナイトワーク業界はジャンル選びと体験が大切
ナイトワークと一言で言ってもたくさんのジャンルがあり、そのジャンルの中でも多くのお店があるので、自分に合ったものは何か、働きやすい場所を探してみると失敗が少ないです。また、週にどれくらい働きたいのか?どれくらいの稼ぎを目指すのかでも選ぶお仕事は変わっていきます。
そして自分の生活スタイルに合わせた働き方をすることも大切です。例えば、朝型の人が深夜まで働くことが難しい場合は、早めに閉店するスナックなどが適しているかもしれません。風俗などは日中働けるお店も多いほか、水商売では朝・昼キャバなどもあります。もともと朝に弱い方は逆に朝方まで営業しているお店がしっくりくる場合も。
ナイトワークはお客様と接することが多いため、人とのコミュニケーションが苦手な方は少しハードルが高いかもしれません。しかし、接客スキルを身につけることで、自信を持って仕事に取り組めるようになるでしょう。まずはなんでも体験!
自分に合ったお店で、輝いて働いてみてくださいね。](https://w-terrace.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)