同伴出勤前、常連客である公輔と手を繋ぎ、科学技術センターから出てくるミユキの足取りは軽く、上機嫌だった。
館内で体感したアトラクションが幼少の頃と変わっておらず、懐かしさで胸がいっぱいになったのもあったが、これから2人で食べに行く中華料理の味を、もうすぐ公輔と共有できることが嬉しくて仕方なかったのだ。
「なんて名前だっけ?今から行く中華の店」
公輔の質問に、ミユキは弾む声で答える。
「サイカイだよー。西の海って書いて、西海」
「西海かー。何が美味しいんだっけ」
「肉丼っ!もう西海に行ったら肉丼しか頼めないんだよね」
「そんなに美味いんだ」
「正直、肉丼とちゃんぽんがぶっちぎりで美味しいと思う。でも、1人だと両方は食べれないから、いつも肉丼しか頼めなくってさ…」

関連ランキング:中華料理 | 藤森駅、龍谷大前深草駅、稲荷駅
「じゃあ、今日は肉丼とちゃんぽんと、2つ頼んだらいいじゃん」
「やーったー!いいのー!?」
「当たり前じゃん」
「あたり前田のクラッカー?」
「あははっ!よくそんな昔のギャグ知ってるね」
ミユキが母に教えてもらった古いネタを炸裂させると、公輔はいつも目を細めて喜び、ミユキの頭をよしよしと撫でてくれるのだった。
店内はかなり客が入っていて、運良くカウンターの空いている席に2人並んで座ることができた。
「生ビール2つと、肉丼とちゃんぽんでお願いしまーす」
「あいよーっ!肉丼、ちゃんぽーん!」
店内に威勢の良い声が響き渡る。
「ミユキちゃんは、ホント色んな美味しい店知ってるな」
「いやー、だってこの辺、超地元だからさ」
「じゃあ、昔よく来てたの?」
「うん。この店、美味しいのに安いから、多い時は週8くらいで通ってたよ」
「週8!?」
「ほんとほんと。1日2回来てたこともあるもん」
「マジ!?じゃ、週8で肉丼ってこと?」
「そうっ!肉丼一筋!」
そんな会話をしながらも、2人の視線は厨房で手際良く具材を炒める料理人の鮮やかな手付きに釘付けだった。
「ずっと見てられるね。スゲー華麗な手さばきだな」
「でしょ?ここホントに出てくるの早くてビックリするよ!」
「美味い、安い、早いって、3拍子揃ってんだ」
「私さ、あまりにも1人で通うから、お店の人に顔覚えられちゃってたみたいで…」
「そりゃそうだろうな」
「1回、めちゃくちゃ思い切って、ちゃんぽん頼んだことあるの。そしたらさー…」
「はいよ、肉丼、お待ちーーー!」
あまりの早さで肉丼が出て来たため、ミユキは肝心のオチの手前で、話を遮られる形になってしまった。
勢いで最後まで話し切ってしまおうかとも思ったが、目の前に差し出されたホカホカで出来たてな肉丼の魅力には勝てそうになかったため、そのまま2人で肉丼に喰らいつくことにしたのだった。
「いただきまーす!」
「はいよ、ちゃんぽん、お待ちーーー!」
久しぶりに食べる肉丼の、甘辛いタレの旨味に悶絶しながら、ミユキはあの時の光景を思い出していた。
日が暮れる少し前の、客がまばらな店内にて。いつも通りカウンターの席に着き、少しだけメニューを見てから「すみません、ちゃんぽんください」とオーダーしたところ「えっ!?ちゃんぽん!?」と、店の人に驚かれてしまったのだ。
その後、「おい!肉丼じゃないってよ!」「え、なに、肉丼じゃない!?」という会話が厨房で繰り広げられた後、作りかけていた肉丼を、大至急ちゃんぽんに変更している様子を肌で感じ取りながら、ミユキは申し訳ないような、ちょっぴり嬉しいような、複雑な気持ちを噛み締めていた。
「ごちそうさまでした!あー、美味しかった、やっぱり最っ高!」
「いやー、マジで最高だったな。肉丼も、ちゃんぽんも、確かに絶品だったよ!」
「でしょ?わかってもらえてよかったー」
ミユキは、公輔とまたこの店に来れば、ずっと気になっていた肉丼とちゃんぽん以外のメニューも食べられるかもしれない、なんて思った。
そして、次に来る時こそは、注文したものが届く前に、例のネタを喋り終えてやろうと誓うのだった。







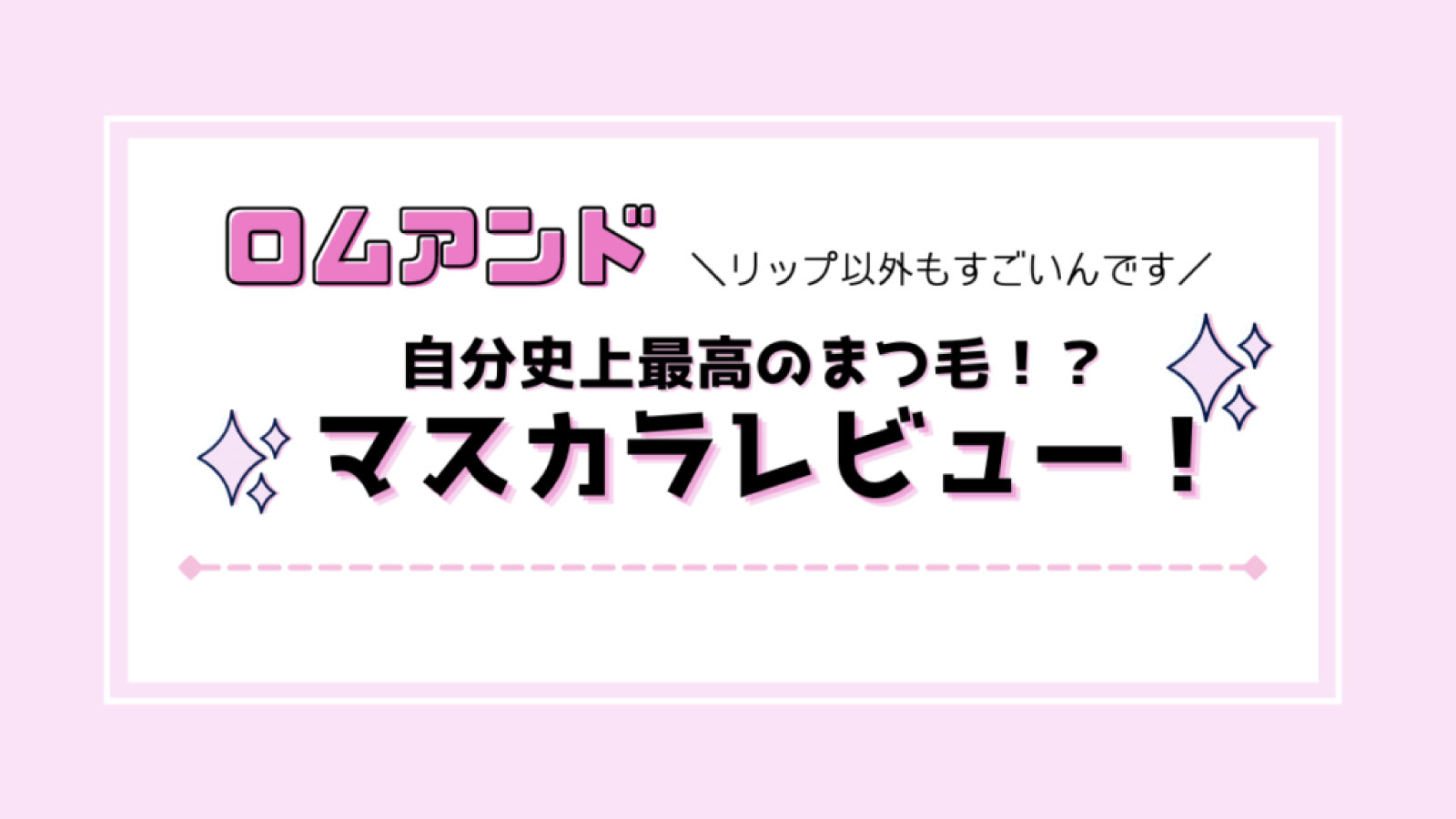



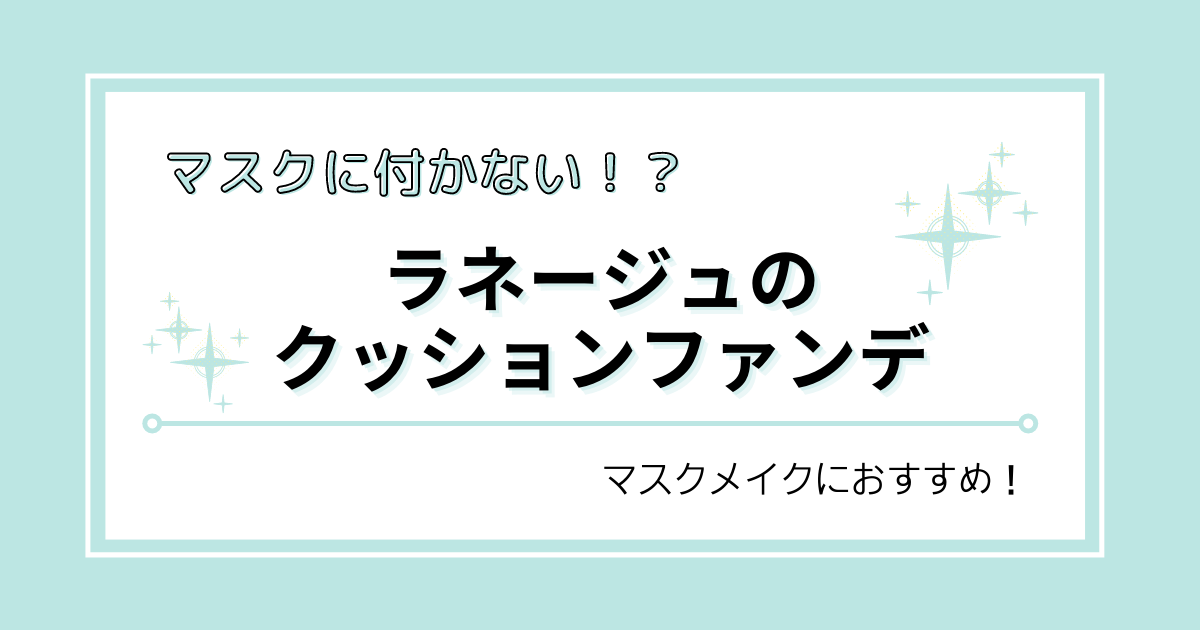






![.
💛夜職デビュー!ナイトワーク初心者向けの業界ガイド💛
ナイトワークをしてみたいけどよくわからない…という方に向けて、どういった風にナイトワークを探していけばいいか、わかりやすいガイドを書いてみました。初心者でわけもわからずになんとなくスマホでポチポチ~っと検索したら出てきたお店に入って「思ったのじゃなかった…」と失敗、なんて残念なことにならないように。まずは下準備をしてみることから始めましょう!
1️⃣ナイトワークの選び方!自分の働き方を見つけるには?
夜のお仕事というと札束!ドレス!スーツ!キラキラ輝く世界!かけひき!
…というイメージがありますが、まぁあながち間違ってはいません。それはさておき。まずは夜職選びの際に決めることは「本業」とするのか「副業・アルバイト」として働いていくのかで大きく変わってきます。
[ナイトワークを副業とする際の注意点]
まず本職が副業OKなのかどうかの確認が必須です。本業の少し足しにしたくて始めたのに、バレて本業がクビになってしまっては本末転倒!!それからたとえ副業がOKの会社だったとしても「ナイトワークで働く社員がいる」ということは、会社のイメージを損なうからという理由で本業にペナルティを追う場合もあります。
副業として行う場合、ナイトワークがバレないように気を付けるることにとにかく気を配ってください!地域を考慮することや、同僚や上司にバレにくい会員制の高級なお店にするなど、対策を考えておくことが大切です。
ただ、会員制のお店で社長とエンカウント!という可能性もあるので、バレにくい地域にするのが適策ですね。本職の会社からなるべく離れた地域をおすすめします。飲みに来た上司軍団に囲まれて逃げ場が無くなるなんてこともあり得ます。
自分の通える範囲でナイトワークがある地域、バレにくい穴場探しをしてみましょう。
[ナイトワークを本業とする際のお店探し]
ナイトワーク一本で働いていく場合、自分に合っている仕事がどういったものなのかやどれくらい月に稼げるかをしっかりと調べる必要があります。時間帯なども、生活リズムを変えていけるのか、日中働いていきたいのか。そういったことにも注目してみてください。
ナイトワークと一言で言っても細かく色々なジャンルがあります。
◯水商売
キャバクラ、クラブ、ガールズバー、ラウンジ、コンパニオンなど
◯風俗
デリバリーヘルス、ソープ、性感エステなど
◯その他ナイトワーク
メンズエステ、チャットレディなど。
男性も同じです!男性のナイトワークと言えばホストが有名ですがメンズバー、メンズパブ、女性用風俗など色々な働き方法がありますよ!
まずはこの大きなジャンルの中から自分が働いてみたいジャンルは何か決めましょう。
[体験入店をうまく利用しよう!]
ナイトワークでは通称「体入」という一日体験入店が出来るお店がほとんどです。お店によっては何度か体入できるお店も。
自分がどういう仕事が合ってるのかわからない場合、色々なジャンルのお店で一日体験として働いて決めてみるといいでしょう。もちろん、体験入店だけでもお給料はしっかりもらえるので安心してくださいね!
ナイトワークの体入はお店の求人サイトや、直接電話やLINEなどをして決めることが出来ます。「人が足りてないから今日すぐに来て!!」と言われることも珍しくないので、心の準備をしておきましょう。
2️⃣ナイトワーク業界はジャンル選びと体験が大切
ナイトワークと一言で言ってもたくさんのジャンルがあり、そのジャンルの中でも多くのお店があるので、自分に合ったものは何か、働きやすい場所を探してみると失敗が少ないです。また、週にどれくらい働きたいのか?どれくらいの稼ぎを目指すのかでも選ぶお仕事は変わっていきます。
そして自分の生活スタイルに合わせた働き方をすることも大切です。例えば、朝型の人が深夜まで働くことが難しい場合は、早めに閉店するスナックなどが適しているかもしれません。風俗などは日中働けるお店も多いほか、水商売では朝・昼キャバなどもあります。もともと朝に弱い方は逆に朝方まで営業しているお店がしっくりくる場合も。
ナイトワークはお客様と接することが多いため、人とのコミュニケーションが苦手な方は少しハードルが高いかもしれません。しかし、接客スキルを身につけることで、自信を持って仕事に取り組めるようになるでしょう。まずはなんでも体験!
自分に合ったお店で、輝いて働いてみてくださいね。](https://w-terrace.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)