ミユキが最近知り合った客の男、慶太はセンスのいいスポーツカーに乗っていて、休日になるとミユキをドライブデートに連れ出してくれた。
この日は2人で午前中から待ち合わせ、新緑の美しい貴船で、川床料理を楽しむことになっていた。
川床とは、京都ならではの文化。山奥にある清流の上に、屋形船のような雰囲気のお座敷が組み立てられており、そこで採れたての鮎をはじめとする懐石料理を味わえるのだ。
「んーーー!んまーーーいっ」
焼かれた鮎の上に軽くスダチを絞り、頭から勢い良くかぶりつく。
ホロ苦い鮎の身はまだ熱々で、そこに絡みつく程良い酸味が食欲をさらに刺激する。
ミユキは座敷の上に仰向けに寝転がりそうになるほど、その鮎の美味さに酔いしれた。
「やっぱ最高だわ、ミユキちゃんのリアクションは。だからこうやって、色んなとこ連れて来たくなっちゃうんだよな」
そう言う慶太の服の裾を掴み、ミユキはさらにジタバタと悶絶した。
「だってホントに美味しいんだもんっ…」
至近距離にある小さな滝からは、ザーッという涼しげな音が終始響いている。まさにマイナスイオンに包まれている異空間といったところだ。
滝をバックに2人で自撮りの記念撮影をしていると、デザートを運びに来た店員さんが声を掛けて来た。
「あちらの席で、流しそうめんを楽しんで頂くこともできますが、どうなさいますか?」
「流しそうめんっ!?」
ミユキの瞳がキラッと輝いたのを横目で見ていた慶太は、すぐに「お願いします」と申し出た。
「え、いいの?流しそうめん、体験させてもらえるんだ」
「当たり前じゃん。俺、ミユキちゃんのリアクション大好物なんだから」
「マジでー!?私、流しそうめん人生初だよ!」
「そっか。じゃあ、初めてを奪えちゃうわけだ」
「キャハハッ!」
流しそうめんの専用席に移動すると、店員さんが簡単にシステムの説明をしてくれた。
「こちらのレーンに流れてくるそうめんをお取りください。赤いそうめんが流れて来たら、その時点で終了となりますので」
「はーい!」
2人並んで座り、箸とめんつゆの入った器を持って待機する。
「なんか緊張するよな」
「ちゃんとキャッチできるかな…」
「あ、ミユキちゃん、来たよ!来た来た!」
ミユキは、流しそうめんのことをよく知らず、絶え間なく流れている麺を、好きなタイミングでつまみあげるのだとばかり思っていたが、実際はしっかり絡まった麺の塊が、一定の感覚を空けて流れてくるシステムなのだった。
「おぉーっ!掴めたー!」
「うおっ、もう次が来てるよ、ミユキちゃん」
「ひょっと待って…、まだ食べれてな…、ふっ…ふがふが…」
「ちょっとちょっと!早く掴まないと!」
「ヤバイよ、これわんこそばのペースじゃんっ」
ミユキは、わんこそばも未経験だったが、予想外に早いペースで流れてくるそうめんを次々に口に放り込むこの感覚は、わんこそばを食べる時のそれに似ていると直感していた。
「んーっ!んううーっ!…待って…待ってぇ…」
「ミユキちゃん、次、次!ちょ、アハハっ!忙しいな、コレ」
2人ではしゃぎ合いながら、そうめんを頬張っていると、目の前に薄いピンク色をしたそうめんの塊が流れて来た。
「あっ、これがさっき言ってた最後のヤツか?」
ミユキの器に、まだ大量の白いそうめんが入っていることを確認した慶太は、咄嗟にピンク色の塊を掴みあげ、自分の器に入れた。
そして…
「赤いそうめんって2人分、来るのかなぁ〜」
なんて言いながら、何気なく薄ピンクの麺を頬張ったのだが…
「んっ!!!なんだこれ、めっちゃ美味い!紫蘇の味がする」
「え、なに…シソ?」
帰りの車の中で、慶太はまだ首をひねり、ちょっぴり悔しそうにしていた。
「そんなに美味しかったの?シソそうめん」
「そうなんだよ、ミユキちゃんのリアクションが見たかったなぁ〜」
「アハハ!そっかー、食べてみたかったな。幻の赤そうめんだね〜」
2人の乗った車は、竹筒の中を流れる赤いそうめんのように、華麗に貴船の細い山道を下っていくのだった。










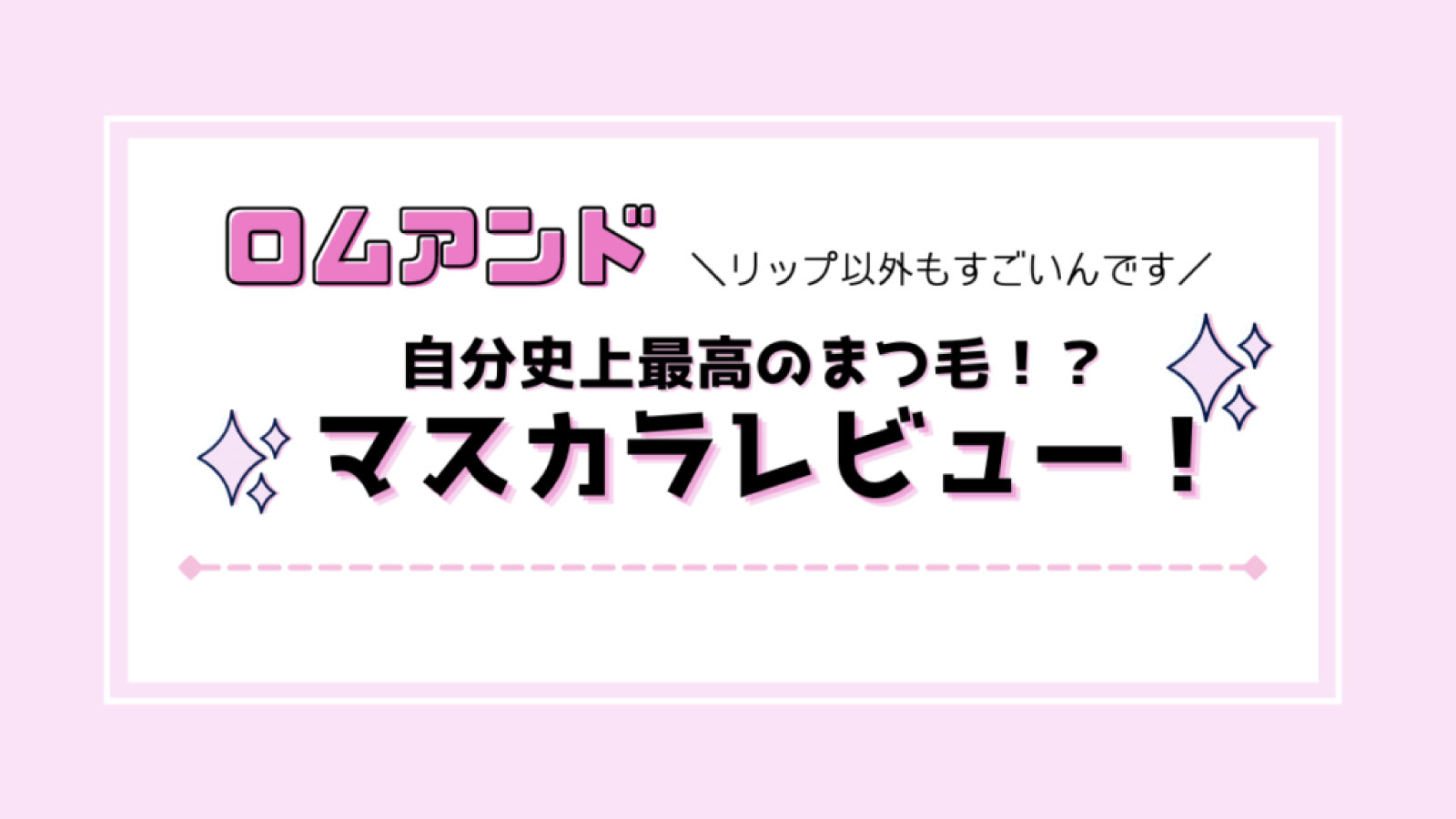







![.
💛夜職デビュー!ナイトワーク初心者向けの業界ガイド💛
ナイトワークをしてみたいけどよくわからない…という方に向けて、どういった風にナイトワークを探していけばいいか、わかりやすいガイドを書いてみました。初心者でわけもわからずになんとなくスマホでポチポチ~っと検索したら出てきたお店に入って「思ったのじゃなかった…」と失敗、なんて残念なことにならないように。まずは下準備をしてみることから始めましょう!
1️⃣ナイトワークの選び方!自分の働き方を見つけるには?
夜のお仕事というと札束!ドレス!スーツ!キラキラ輝く世界!かけひき!
…というイメージがありますが、まぁあながち間違ってはいません。それはさておき。まずは夜職選びの際に決めることは「本業」とするのか「副業・アルバイト」として働いていくのかで大きく変わってきます。
[ナイトワークを副業とする際の注意点]
まず本職が副業OKなのかどうかの確認が必須です。本業の少し足しにしたくて始めたのに、バレて本業がクビになってしまっては本末転倒!!それからたとえ副業がOKの会社だったとしても「ナイトワークで働く社員がいる」ということは、会社のイメージを損なうからという理由で本業にペナルティを追う場合もあります。
副業として行う場合、ナイトワークがバレないように気を付けるることにとにかく気を配ってください!地域を考慮することや、同僚や上司にバレにくい会員制の高級なお店にするなど、対策を考えておくことが大切です。
ただ、会員制のお店で社長とエンカウント!という可能性もあるので、バレにくい地域にするのが適策ですね。本職の会社からなるべく離れた地域をおすすめします。飲みに来た上司軍団に囲まれて逃げ場が無くなるなんてこともあり得ます。
自分の通える範囲でナイトワークがある地域、バレにくい穴場探しをしてみましょう。
[ナイトワークを本業とする際のお店探し]
ナイトワーク一本で働いていく場合、自分に合っている仕事がどういったものなのかやどれくらい月に稼げるかをしっかりと調べる必要があります。時間帯なども、生活リズムを変えていけるのか、日中働いていきたいのか。そういったことにも注目してみてください。
ナイトワークと一言で言っても細かく色々なジャンルがあります。
◯水商売
キャバクラ、クラブ、ガールズバー、ラウンジ、コンパニオンなど
◯風俗
デリバリーヘルス、ソープ、性感エステなど
◯その他ナイトワーク
メンズエステ、チャットレディなど。
男性も同じです!男性のナイトワークと言えばホストが有名ですがメンズバー、メンズパブ、女性用風俗など色々な働き方法がありますよ!
まずはこの大きなジャンルの中から自分が働いてみたいジャンルは何か決めましょう。
[体験入店をうまく利用しよう!]
ナイトワークでは通称「体入」という一日体験入店が出来るお店がほとんどです。お店によっては何度か体入できるお店も。
自分がどういう仕事が合ってるのかわからない場合、色々なジャンルのお店で一日体験として働いて決めてみるといいでしょう。もちろん、体験入店だけでもお給料はしっかりもらえるので安心してくださいね!
ナイトワークの体入はお店の求人サイトや、直接電話やLINEなどをして決めることが出来ます。「人が足りてないから今日すぐに来て!!」と言われることも珍しくないので、心の準備をしておきましょう。
2️⃣ナイトワーク業界はジャンル選びと体験が大切
ナイトワークと一言で言ってもたくさんのジャンルがあり、そのジャンルの中でも多くのお店があるので、自分に合ったものは何か、働きやすい場所を探してみると失敗が少ないです。また、週にどれくらい働きたいのか?どれくらいの稼ぎを目指すのかでも選ぶお仕事は変わっていきます。
そして自分の生活スタイルに合わせた働き方をすることも大切です。例えば、朝型の人が深夜まで働くことが難しい場合は、早めに閉店するスナックなどが適しているかもしれません。風俗などは日中働けるお店も多いほか、水商売では朝・昼キャバなどもあります。もともと朝に弱い方は逆に朝方まで営業しているお店がしっくりくる場合も。
ナイトワークはお客様と接することが多いため、人とのコミュニケーションが苦手な方は少しハードルが高いかもしれません。しかし、接客スキルを身につけることで、自信を持って仕事に取り組めるようになるでしょう。まずはなんでも体験!
自分に合ったお店で、輝いて働いてみてくださいね。](https://w-terrace.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)