同伴デート中、「ミユキちゃんの今、一番の夢って何なの?」と突然、公輔に尋ねられたミユキは、食べ物のことしか思い浮かべられなかった。
「こんな大それたこと、口にしていいのかわからないけど…」
「え?うん、なになに?」
「てっさを…」
「てっさを?」
「お箸で端から端までザーッ!…て」
ミユキの頭の中には、美しく扇状に並べられた透明なふぐの刺身皿が鮮明に浮かんでいた。
人生の中でも数回しか食べたことのないふぐ刺を、ミユキはいつもチビチビと1切れずつ食べていた。もちろん、その理由は「一度に食べてしまったらもったいないから」だ。
「マジかー!でも、それが確かに大それた夢って言うの、わかるよ」
「でしょ?」
「実際、本物を前にしたらザーッとはいけないもんだよ」
「だよね?そうだよね?」
そんなわけで、ミユキは公輔に、金閣寺の近くにあるふぐ料理の専門店『ともえ』に連れて来てもらうのだった。
「どう?ミユキちゃん!ついに、念願の…だよ」
「叶っちゃうのかな、私の夢」
1人前ずつ、小皿に丁寧に並べられたふぐの身を、ミユキは端から箸ですくいあげたのだが、その動きは1切れを救いあげたところでピタリと止まってしまった。
それは、女将さんの突き刺さるような視線を感じたからだ。
この店は、ふぐに対するこだわりが異常なまでに強く、視線を送るどころか、正しい食べ方を最初から最後まで徹底的に管理するような状態だった。もちろん、良かれと思ってなのだが…
「まずは、この塩で1切れいってちょうだいね〜」
「…はいっ」
「そのあと、このポン酢でまた一切れ食べて。それからこの白子を少し溶かして〜…」
ミユキは売れっ子キャバ嬢をやっているだけあって、自分の意見はきちんと言える方だったが、それでも、この状況で「もう一思いにザーッといっちゃっていいっすか?」とは言えない、空気を読んでしまうタイプの女だった。
女将さんのふぐに対する熱量トークは、ふぐを網で焼いている時も、唐揚げが登場した時も、鍋がやってきた時も、無限と思えるほどに続いていく。
「ふぐの店言うたら、他にもぎょうさんあるけど、ほんまもんはうちだけよ」
「そうなんですね〜」
「他の店のはどうしても生臭くなってしまうんやけど、うちのは特別でね…」
普通のキャバ嬢だったら、お客さんとの会話を考えなくても、女将さんが仕切ってくれるので、こりゃ楽だ!なんて思いそうなものだが、ミユキは公輔とトークを楽しむのが純粋に好きだったので、全く会話が成立しない状況に対し、一抹の寂しさを感じ始めていた。
このふぐは、ヤバイ!ウマイ!最高過ぎる!そう叫んで盛り上がりたいのだが、女将さんの手前、どうしても借りてきた猫のようになってしまい、リアクションが取れないのだ。
ミユキは、座敷で公輔と向かい合わせに座っていたのだが、途中から席を隣同士の位置に移動し、ピタッと寄り添った。
「あら、仲良しね〜。お隣に移動したの?」
「えへへ」
テーブルの下で公輔に手をつないでもらい、ミユキはようやくふぐの美味しさに集中し始めることができた。
鍋が終わりに差し掛かる頃、チラチラと公輔の方を見ていた女将さんが、「え〜っと…、誰やったかな」と何やら考え込むような仕草を見せた。
「お兄さん、誰かに似てるんよね…、ほら、あの…、ジャニーズの」
「え、ジャニーズですか!?」
「ハム輔イケメン確定じゃん」
「誰やったかな、ぶい…ぶいしっくすの…、えーっと、ナカ…ナカなんとか君」
「V6に、ナカなんとか君なんていましたっけ?」
「ナカ…ナカ…、えーっと、朝の番組に出とるんやけどな」
暖簾をくぐって店を出ると、2人は「ハーッ…」と幸せな深いため息をついた。
「最後の白子のスープ…、あれはヤバかったね」
「ヤバかった。あれは記憶吹き飛ぶレベルの美味さだったよ」
「最高だったね〜、ナカなんとか君」
「ふふっ、誰のことだったんだろう」
「誰だったとしても、ジャニーズならイケメンに間違いないよ」
そして、2人はまた仲良く手をつなぎ、思う存分ふぐの美味しさについて語り合うのだった。








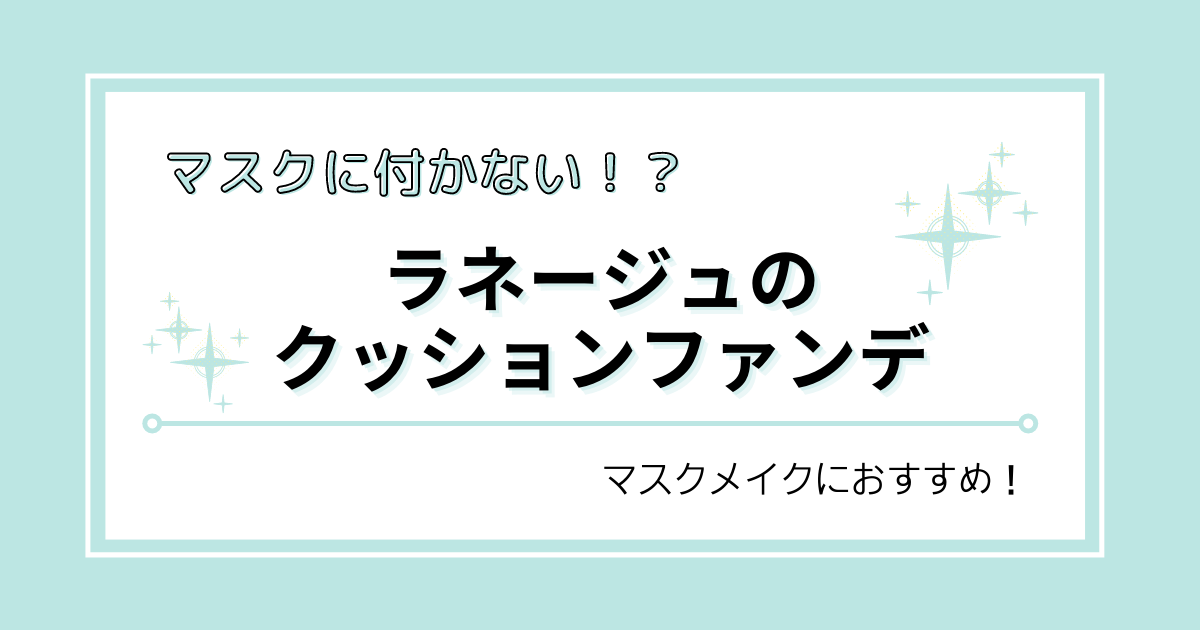
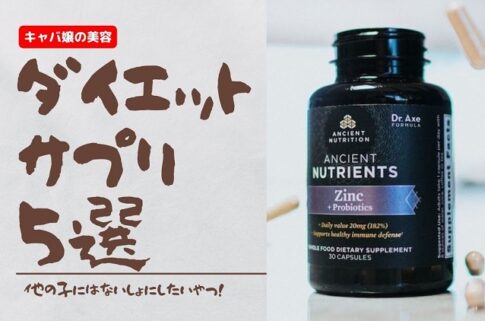








![.
💛夜職デビュー!ナイトワーク初心者向けの業界ガイド💛
ナイトワークをしてみたいけどよくわからない…という方に向けて、どういった風にナイトワークを探していけばいいか、わかりやすいガイドを書いてみました。初心者でわけもわからずになんとなくスマホでポチポチ~っと検索したら出てきたお店に入って「思ったのじゃなかった…」と失敗、なんて残念なことにならないように。まずは下準備をしてみることから始めましょう!
1️⃣ナイトワークの選び方!自分の働き方を見つけるには?
夜のお仕事というと札束!ドレス!スーツ!キラキラ輝く世界!かけひき!
…というイメージがありますが、まぁあながち間違ってはいません。それはさておき。まずは夜職選びの際に決めることは「本業」とするのか「副業・アルバイト」として働いていくのかで大きく変わってきます。
[ナイトワークを副業とする際の注意点]
まず本職が副業OKなのかどうかの確認が必須です。本業の少し足しにしたくて始めたのに、バレて本業がクビになってしまっては本末転倒!!それからたとえ副業がOKの会社だったとしても「ナイトワークで働く社員がいる」ということは、会社のイメージを損なうからという理由で本業にペナルティを追う場合もあります。
副業として行う場合、ナイトワークがバレないように気を付けるることにとにかく気を配ってください!地域を考慮することや、同僚や上司にバレにくい会員制の高級なお店にするなど、対策を考えておくことが大切です。
ただ、会員制のお店で社長とエンカウント!という可能性もあるので、バレにくい地域にするのが適策ですね。本職の会社からなるべく離れた地域をおすすめします。飲みに来た上司軍団に囲まれて逃げ場が無くなるなんてこともあり得ます。
自分の通える範囲でナイトワークがある地域、バレにくい穴場探しをしてみましょう。
[ナイトワークを本業とする際のお店探し]
ナイトワーク一本で働いていく場合、自分に合っている仕事がどういったものなのかやどれくらい月に稼げるかをしっかりと調べる必要があります。時間帯なども、生活リズムを変えていけるのか、日中働いていきたいのか。そういったことにも注目してみてください。
ナイトワークと一言で言っても細かく色々なジャンルがあります。
◯水商売
キャバクラ、クラブ、ガールズバー、ラウンジ、コンパニオンなど
◯風俗
デリバリーヘルス、ソープ、性感エステなど
◯その他ナイトワーク
メンズエステ、チャットレディなど。
男性も同じです!男性のナイトワークと言えばホストが有名ですがメンズバー、メンズパブ、女性用風俗など色々な働き方法がありますよ!
まずはこの大きなジャンルの中から自分が働いてみたいジャンルは何か決めましょう。
[体験入店をうまく利用しよう!]
ナイトワークでは通称「体入」という一日体験入店が出来るお店がほとんどです。お店によっては何度か体入できるお店も。
自分がどういう仕事が合ってるのかわからない場合、色々なジャンルのお店で一日体験として働いて決めてみるといいでしょう。もちろん、体験入店だけでもお給料はしっかりもらえるので安心してくださいね!
ナイトワークの体入はお店の求人サイトや、直接電話やLINEなどをして決めることが出来ます。「人が足りてないから今日すぐに来て!!」と言われることも珍しくないので、心の準備をしておきましょう。
2️⃣ナイトワーク業界はジャンル選びと体験が大切
ナイトワークと一言で言ってもたくさんのジャンルがあり、そのジャンルの中でも多くのお店があるので、自分に合ったものは何か、働きやすい場所を探してみると失敗が少ないです。また、週にどれくらい働きたいのか?どれくらいの稼ぎを目指すのかでも選ぶお仕事は変わっていきます。
そして自分の生活スタイルに合わせた働き方をすることも大切です。例えば、朝型の人が深夜まで働くことが難しい場合は、早めに閉店するスナックなどが適しているかもしれません。風俗などは日中働けるお店も多いほか、水商売では朝・昼キャバなどもあります。もともと朝に弱い方は逆に朝方まで営業しているお店がしっくりくる場合も。
ナイトワークはお客様と接することが多いため、人とのコミュニケーションが苦手な方は少しハードルが高いかもしれません。しかし、接客スキルを身につけることで、自信を持って仕事に取り組めるようになるでしょう。まずはなんでも体験!
自分に合ったお店で、輝いて働いてみてくださいね。](https://w-terrace.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)