その週末、ミユキは東京で暮らす母の元を訪ねていた。
ミユキは思春期の頃から京都暮らしだが、生まれたのは千葉県だった。両親も関東の人間なので、ミユキが関西弁でないのも、そのためだ。
小さい頃の千葉の思い出といえば、駅弁の『菜の花弁当』だ。
ミユキの両親は共働きだったので、母は菜の花弁当で夕飯を済ませようとすることが多かった。「今日も菜の花弁当でごめんね」と、母はいつも申し訳なさそうにしていたが、ミユキはそれが嬉しかった。
菜の花弁当は、ご飯の上に、鶏そぼろと炒りたまごが乗っており、煮たアサリの串や紅しょうが、お漬物が付いているだけのシンプルなものだったが、ミユキは素朴なその味がなんとも言えず好きだったのだ。
母の顔を見ると必ず、菜の花弁当が食べたくなるのだが、菜の花弁当は限られた駅でしか売られていないため、ミユキはもう長年、菜の花弁当を味わえていなかった。
そんな時、キャバクラの客である聡太からLINEで連絡が入ったものだから、ミユキはついつい、ワガママなオーダーをしてしまうのだった。
「ミユキちゃん、今東京に来てるんでしょ?」
「うん、そうだよ」
「俺、今出張から帰ってきて、成田空港に到着したとこなんだ」
「ウソ、じゃあ、会えちゃったりする?」
「会おうよ!なんかお土産買っていくけど、何がいい?」
「ホント!?じゃ、菜の花弁当がいい!」
「菜の花弁当…?よくわかんないけど、駅とかで売ってるの?」
「うん!私の思い出の味なんだ〜」
「そっか。じゃあ、探して買っていくよ」
しばらく経ってから、ミユキは菜の花弁当が、千葉駅の構内でしか買えないことをボンヤリ思い出していた。
千葉方面から帰ってくると聞いてつい、勢いでオーダーしてしまったのだが、聡太は成田空港から帰ってくると言っていた。
空港から東京へ帰って来る人は、大抵『成田エクスプレス』に乗るものだ。つまり、東京まで乗換なしで一直線に帰って来るわけで…。
ミユキは「お土産、別になくても大丈夫だよ〜」と、文章を打ちかけたのだが、キッチンにいる母親に呼ばれたことがキッカケで、そのメッセージは送らないまま保留となってしまった。
数時間後…
東京駅で聡太を出迎えたミユキは、手渡されたビニール袋の中身を見て驚愕するのだった。
「えっ…!?菜の花弁当、どうして!?」
「どうしてって、食べたいって言ってたじゃん」
「だって成田から直通で東京まで来たんじゃないの?」
「いや、千葉駅で1回降りたよ。調べたら千葉駅でしか売ってなかったからさ」
ミユキは、袋の中にある赤地に黄色の可愛らしいパッケージが、視界の中でうるうるとボヤけていくのを感じながら、震えそうな唇を噛み締めていた。
「うっ…、ありがと…」
「ハハッ!めっちゃ感激してくれてるじゃん」
「だって…、わざわざ降りてくれるなんてさ」
聡太は、当然のように千葉駅で降りたと言っていたが、ミユキにとっては、そうまでして菜の花弁当を買って来てくれた聡太の気持ちが、信じられないほど嬉しかった。
「せっかくだし、一緒に食べようよ。この辺、どっか景色のいいとこあるかな」
空は、薄いピンク色に染まり始めたところだった。
ミユキと聡太は、並んで菜の花弁当の蓋を開ける。
「へー、菜の花弁当って意外にシンプルなんだね」
「そうなんだけど、マネして作っても、絶対この味にはならないんだよ」
「え、マネして作ったことあるの?」
「そぼろに卵だから簡単そうだけど、こんな優しい味にはならなくて…」
「確かに優しい味だね」
「うん、聡太みたいに優しい味」
「あはは、また、そういうこと言って…」
「だってホントだもん。ホントに嬉しかったんだもん」
アサリの串を咥えながら、ミユキは聡太の肩にもたれかかり、紅しょうが色の光の中でそっと目を閉じた。





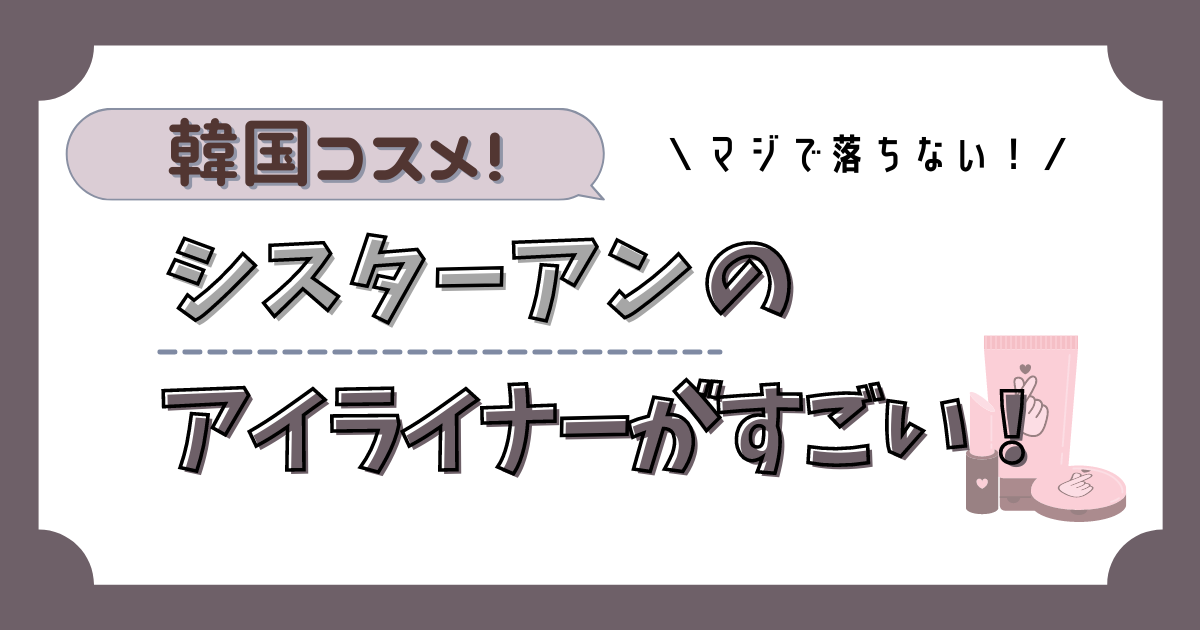












![.
💛夜職デビュー!ナイトワーク初心者向けの業界ガイド💛
ナイトワークをしてみたいけどよくわからない…という方に向けて、どういった風にナイトワークを探していけばいいか、わかりやすいガイドを書いてみました。初心者でわけもわからずになんとなくスマホでポチポチ~っと検索したら出てきたお店に入って「思ったのじゃなかった…」と失敗、なんて残念なことにならないように。まずは下準備をしてみることから始めましょう!
1️⃣ナイトワークの選び方!自分の働き方を見つけるには?
夜のお仕事というと札束!ドレス!スーツ!キラキラ輝く世界!かけひき!
…というイメージがありますが、まぁあながち間違ってはいません。それはさておき。まずは夜職選びの際に決めることは「本業」とするのか「副業・アルバイト」として働いていくのかで大きく変わってきます。
[ナイトワークを副業とする際の注意点]
まず本職が副業OKなのかどうかの確認が必須です。本業の少し足しにしたくて始めたのに、バレて本業がクビになってしまっては本末転倒!!それからたとえ副業がOKの会社だったとしても「ナイトワークで働く社員がいる」ということは、会社のイメージを損なうからという理由で本業にペナルティを追う場合もあります。
副業として行う場合、ナイトワークがバレないように気を付けるることにとにかく気を配ってください!地域を考慮することや、同僚や上司にバレにくい会員制の高級なお店にするなど、対策を考えておくことが大切です。
ただ、会員制のお店で社長とエンカウント!という可能性もあるので、バレにくい地域にするのが適策ですね。本職の会社からなるべく離れた地域をおすすめします。飲みに来た上司軍団に囲まれて逃げ場が無くなるなんてこともあり得ます。
自分の通える範囲でナイトワークがある地域、バレにくい穴場探しをしてみましょう。
[ナイトワークを本業とする際のお店探し]
ナイトワーク一本で働いていく場合、自分に合っている仕事がどういったものなのかやどれくらい月に稼げるかをしっかりと調べる必要があります。時間帯なども、生活リズムを変えていけるのか、日中働いていきたいのか。そういったことにも注目してみてください。
ナイトワークと一言で言っても細かく色々なジャンルがあります。
◯水商売
キャバクラ、クラブ、ガールズバー、ラウンジ、コンパニオンなど
◯風俗
デリバリーヘルス、ソープ、性感エステなど
◯その他ナイトワーク
メンズエステ、チャットレディなど。
男性も同じです!男性のナイトワークと言えばホストが有名ですがメンズバー、メンズパブ、女性用風俗など色々な働き方法がありますよ!
まずはこの大きなジャンルの中から自分が働いてみたいジャンルは何か決めましょう。
[体験入店をうまく利用しよう!]
ナイトワークでは通称「体入」という一日体験入店が出来るお店がほとんどです。お店によっては何度か体入できるお店も。
自分がどういう仕事が合ってるのかわからない場合、色々なジャンルのお店で一日体験として働いて決めてみるといいでしょう。もちろん、体験入店だけでもお給料はしっかりもらえるので安心してくださいね!
ナイトワークの体入はお店の求人サイトや、直接電話やLINEなどをして決めることが出来ます。「人が足りてないから今日すぐに来て!!」と言われることも珍しくないので、心の準備をしておきましょう。
2️⃣ナイトワーク業界はジャンル選びと体験が大切
ナイトワークと一言で言ってもたくさんのジャンルがあり、そのジャンルの中でも多くのお店があるので、自分に合ったものは何か、働きやすい場所を探してみると失敗が少ないです。また、週にどれくらい働きたいのか?どれくらいの稼ぎを目指すのかでも選ぶお仕事は変わっていきます。
そして自分の生活スタイルに合わせた働き方をすることも大切です。例えば、朝型の人が深夜まで働くことが難しい場合は、早めに閉店するスナックなどが適しているかもしれません。風俗などは日中働けるお店も多いほか、水商売では朝・昼キャバなどもあります。もともと朝に弱い方は逆に朝方まで営業しているお店がしっくりくる場合も。
ナイトワークはお客様と接することが多いため、人とのコミュニケーションが苦手な方は少しハードルが高いかもしれません。しかし、接客スキルを身につけることで、自信を持って仕事に取り組めるようになるでしょう。まずはなんでも体験!
自分に合ったお店で、輝いて働いてみてくださいね。](https://w-terrace.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)