出勤前に、ボリュームのある料理や、匂いの強い料理はできるだけ食べないようにしているミユキだったが、今日の同伴客は食通な友広ということで、ミユキは自分の中での「切り札」を出すことにした。
ホルモン焼肉の名店『たまらんアジェ』は、あまりにも人気があるため、隣のテナントを待合室として利用しているほどの名店だ。
予約はなかなか受け付けてくれず、当日待たずに食べたければ開店前から早目に店へ行って、直接名前を記入するしかない。
ミユキはぬかりなく、開店15分前に名前を書くと、そこでホッと息をついた。
「よし、これでもう大丈夫」
待ち合わせ場所である鴨川の橋の上で、溜まっていたLINEの返信なんかをしながら、夕方の風に吹かれ、たそがれる。
「お待たせ、ミユキちゃん」
「あー!お久しぶりですー」
「今日、俺めちゃくちゃ楽しみにして来たんだよー、ミユキちゃんが大絶賛する店だから」
「私も楽しみでしたー!友広さんにどうしても食べてもらいたかったから。アジェのホソ」
「ホソ?」
「アジェと言えばホソなんで。さ、行きましょ!もう名前も書いて予約完了してますから」

関連ランキング:ホルモン | 清水五条駅、京都河原町駅、祇園四条駅
ビールで乾杯した後、そのビールの美味さを情緒たっぷりに表現する友広を見て、ミユキはいつも以上にニコニコしていた。
こういうシチュエーションで大袈裟なリアクションをするのは、いつも基本的にキャバ嬢であるミユキの役割なのだが、友広と一緒の時だけ、ミユキは美味しそうに食べる友広の姿を眺める側に回るのだった。
「はーい、こちらがホソ用のタレでーす。こちらが付けダレ用でーす」
初めての店で、一瞬戸惑っている様子の友広に向かって、ミユキは真剣にレクチャーをした。
「友広さん、こっちがホソ用ですから。間違えないでくださいね」
「めちゃくちゃ真顔だな。わかった!これは重要なんだな」
「だって、完璧な状態で食べて欲しいじゃないですか」
「わかる、そういうのって大事だからね」
網の上でしたたる油の中、ゴウゴウと音を立てて燃えているホソを、ミユキは注意深くトングで1つ1つひっくり返していった。友広は「俺がやるよ」と言ってくれたのだが、ミユキは軽く左手でそれを制する。
「いえ、大丈夫です!まず先に皮の面から焼いて、底に汁を溜めて…とか、色々あるんで」
「すげー、こだわるじゃん!ヤバイな、めちゃくちゃ楽しみになってきたよ」
手持ち無沙汰なのか、燃え盛るホソをカシャカシャとスマホに収めている友広から、無限大の期待を感じつつ、ミユキは絶妙のタイミングで、一番に焼き上がったホソを広いあげた。
「さあ!いっちゃってください!」
「いいの!?もういっちゃっていい!?」
「熱いうちに…、さあ早く…」
2番目に焼き上がったホソを、少々ガサツに自分のタレ皿の中へ放り込むと、2人は同時に熱々の塊を頬張った。
「んんんーーー…っ!!!!!」
「…うんっまーーーーー!!!!!」
ミユキは、美味さで悶絶しまくる友広をしっかりこの目に収めなければと思っていたのだが、自分自身も昇天してしまったため、この時の記憶は実際ほとんど脳内に残せなかった。
「なんだこれ!この世に、こんな美味いものあったんだ」
「んー…!んーっ!わかってもらえまひた?友広はん…」
口内をヤケドしないように気をつけつつ、ミユキは友広と特別な幸せを分かち合った。
「これは、死ぬ前に食べたいものベスト3に絶対入るな」
「わかりまふ、わたひもれふ…」
梨ジュースで口の中をサッパリさせてから、ミユキはまた真剣な眼差しに戻る。
「でもね、友広さん。このホソは、食べれるうちに食べたいだけ食べておいた方がいいです」
「え、どういうこと?」
「死ぬ前どこじゃなく、あと10年も経ったら多分もう美味しいって思えなくなっちゃうんですよ、この脂の感じ。うちの親とも一緒に来たことあるんですけど、全然わからなかったみたいですもん、この価値が」
「なるほど…!」
夜の鴨川沿いを歩きながら、友広はミユキに聞こえるか聞こえないかくらいのボリュームで、意味深なことを、噛み締めるように囁いた。
「死ぬ前に…と思って、残しておいちゃいけないんだな。なんだって、そうだ」
脂たっぷりのホソの余韻に浸りながら、ミユキは今頃きちんと消化活動をしてくれている胃や腸があることにそっと感謝をした。





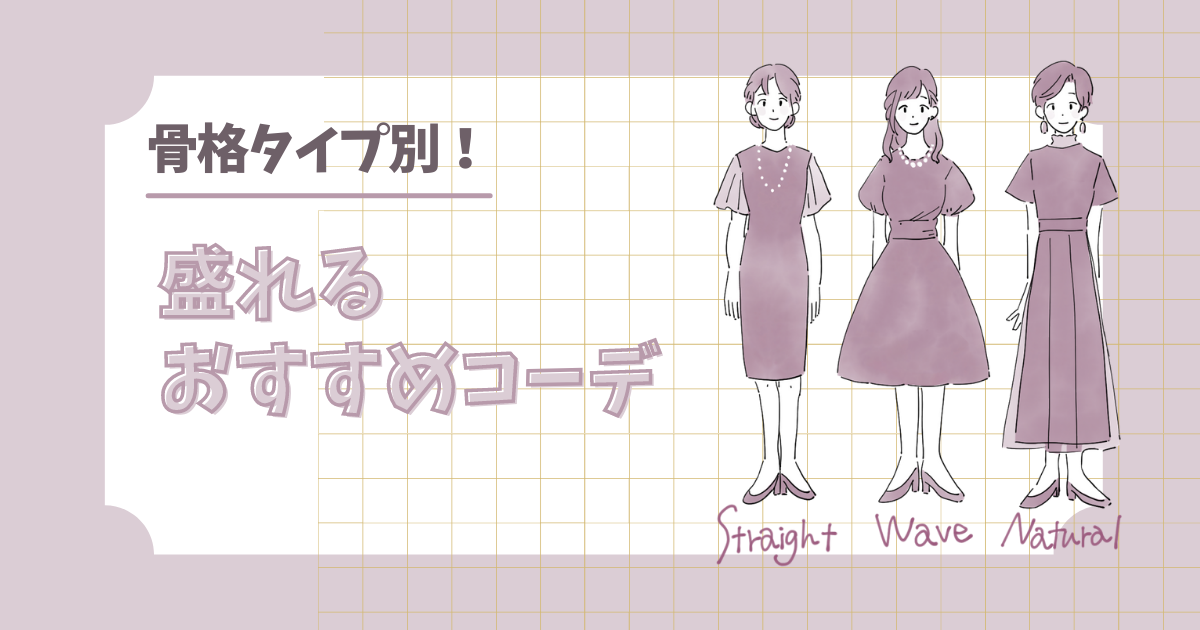

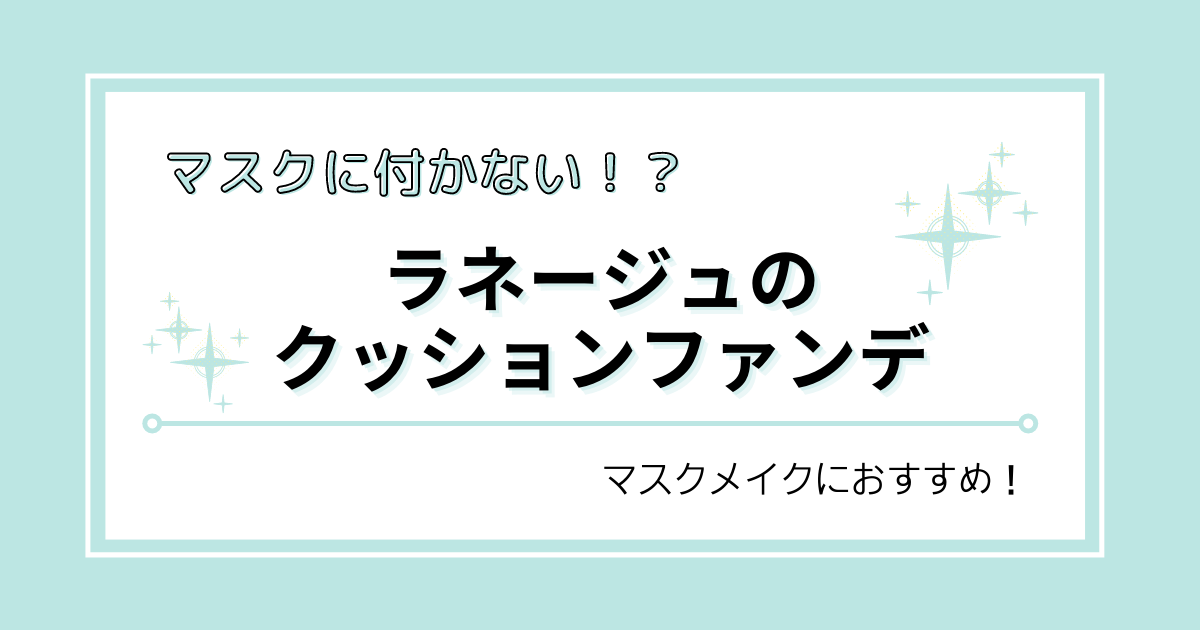










![.
💛夜職デビュー!ナイトワーク初心者向けの業界ガイド💛
ナイトワークをしてみたいけどよくわからない…という方に向けて、どういった風にナイトワークを探していけばいいか、わかりやすいガイドを書いてみました。初心者でわけもわからずになんとなくスマホでポチポチ~っと検索したら出てきたお店に入って「思ったのじゃなかった…」と失敗、なんて残念なことにならないように。まずは下準備をしてみることから始めましょう!
1️⃣ナイトワークの選び方!自分の働き方を見つけるには?
夜のお仕事というと札束!ドレス!スーツ!キラキラ輝く世界!かけひき!
…というイメージがありますが、まぁあながち間違ってはいません。それはさておき。まずは夜職選びの際に決めることは「本業」とするのか「副業・アルバイト」として働いていくのかで大きく変わってきます。
[ナイトワークを副業とする際の注意点]
まず本職が副業OKなのかどうかの確認が必須です。本業の少し足しにしたくて始めたのに、バレて本業がクビになってしまっては本末転倒!!それからたとえ副業がOKの会社だったとしても「ナイトワークで働く社員がいる」ということは、会社のイメージを損なうからという理由で本業にペナルティを追う場合もあります。
副業として行う場合、ナイトワークがバレないように気を付けるることにとにかく気を配ってください!地域を考慮することや、同僚や上司にバレにくい会員制の高級なお店にするなど、対策を考えておくことが大切です。
ただ、会員制のお店で社長とエンカウント!という可能性もあるので、バレにくい地域にするのが適策ですね。本職の会社からなるべく離れた地域をおすすめします。飲みに来た上司軍団に囲まれて逃げ場が無くなるなんてこともあり得ます。
自分の通える範囲でナイトワークがある地域、バレにくい穴場探しをしてみましょう。
[ナイトワークを本業とする際のお店探し]
ナイトワーク一本で働いていく場合、自分に合っている仕事がどういったものなのかやどれくらい月に稼げるかをしっかりと調べる必要があります。時間帯なども、生活リズムを変えていけるのか、日中働いていきたいのか。そういったことにも注目してみてください。
ナイトワークと一言で言っても細かく色々なジャンルがあります。
◯水商売
キャバクラ、クラブ、ガールズバー、ラウンジ、コンパニオンなど
◯風俗
デリバリーヘルス、ソープ、性感エステなど
◯その他ナイトワーク
メンズエステ、チャットレディなど。
男性も同じです!男性のナイトワークと言えばホストが有名ですがメンズバー、メンズパブ、女性用風俗など色々な働き方法がありますよ!
まずはこの大きなジャンルの中から自分が働いてみたいジャンルは何か決めましょう。
[体験入店をうまく利用しよう!]
ナイトワークでは通称「体入」という一日体験入店が出来るお店がほとんどです。お店によっては何度か体入できるお店も。
自分がどういう仕事が合ってるのかわからない場合、色々なジャンルのお店で一日体験として働いて決めてみるといいでしょう。もちろん、体験入店だけでもお給料はしっかりもらえるので安心してくださいね!
ナイトワークの体入はお店の求人サイトや、直接電話やLINEなどをして決めることが出来ます。「人が足りてないから今日すぐに来て!!」と言われることも珍しくないので、心の準備をしておきましょう。
2️⃣ナイトワーク業界はジャンル選びと体験が大切
ナイトワークと一言で言ってもたくさんのジャンルがあり、そのジャンルの中でも多くのお店があるので、自分に合ったものは何か、働きやすい場所を探してみると失敗が少ないです。また、週にどれくらい働きたいのか?どれくらいの稼ぎを目指すのかでも選ぶお仕事は変わっていきます。
そして自分の生活スタイルに合わせた働き方をすることも大切です。例えば、朝型の人が深夜まで働くことが難しい場合は、早めに閉店するスナックなどが適しているかもしれません。風俗などは日中働けるお店も多いほか、水商売では朝・昼キャバなどもあります。もともと朝に弱い方は逆に朝方まで営業しているお店がしっくりくる場合も。
ナイトワークはお客様と接することが多いため、人とのコミュニケーションが苦手な方は少しハードルが高いかもしれません。しかし、接客スキルを身につけることで、自信を持って仕事に取り組めるようになるでしょう。まずはなんでも体験!
自分に合ったお店で、輝いて働いてみてくださいね。](https://w-terrace.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)