しばらくの間、母親のいる東京に滞在することになったミユキは、その日、東京の客と待ち合わせをし、夕飯をごちそうしてもらうことになっていた。
高級なホテルでフレンチなんか奢ってもらってもよかったのだが、ミユキは「それならフォルクスに行きたい」と自ら申し出た。
フォルクスはステーキハウスなので、それなりに高級な存在ではあるが、どちらかというと、雰囲気はファミリーレストランに近い。
客である涼平は、逆に「そんなところでいいの?」と、ちょっぴり物足りなそうな様子だったが、ミユキは「フォルクスがいいです」の一点張りだった。
食べることが大好きなミユキは、本当なら貪欲に豪華なモノを食べたいと思うところなのだが…、あまり慣れない東京の、しかも表参道近辺というオシャレなエリアで、とんでもなく高級なホテルにでも連れて行かれたら、胃を壊しそうだと不安を感じていたのだ。
涼平は紳士的で優しい男だったが、ミユキにとって、そこまで距離感の近い相手ではないため、馴染みのあるフォルクスで、アウェイな空気感を吹き飛ばしたかったのだ。
「フォルクスって日本で初めてサラダバーを導入したレストランなんですよ」
夕日に染まる代々木公園内の静かな道を涼平と並んで歩きながら、ミユキは以前、別の客から教えてもらったフォルクス豆知識を涼平に披露した。
「へー!そうなんだ。ちなみに、サラダバーでミユキちゃんは何を取るの?」
そう尋ねられ、ミユキは心の中でハッと、身構えた。
普段、何気なくサラダバーやスープバーで好きなものをごっそり盛っていたが、見る人が見れば、そこには人間性がモロに現れるのだろう。
「えー…、その時によって、かな。涼平さんは?」
「俺は、何を取るか…っていうよりも、バランス良く盛り付けることを意識するかなぁ」
フォルクス店内にて。
サラダバーの前に皿を持って立った時、ミユキは改めて、涼平と盛り付けの話をしておいてよかったと思った。
そうでなかったら、あぶなく小皿いっぱいに枝豆とコーンを半々ずつ盛り付けてしまうところだった。
正直、ニンジンやタマネギやトマトやブロッコリーにはそこまで心惹かれず。とにかく、枝豆とコーンに和風ドレッシングをたっぷり掛け、それを思い切り口にかきこみたかったのだが…。
ミユキは、涼平に対して見栄を張り、デキる女であることをアピールするために、ほぼ全ての野菜をバランス良く綺麗に盛り付けた。
「お~!綺麗に盛り付けるね。俺、ミユキちゃんますます好きになったわ」
涼平にそう言われ、ミユキは「そうですか〜?」とはにかんで見せたが、内心はちょっぴり複雑だった。
本当は、コーンスープを3カップくらい持って来た上で、枝豆とコーンが半々で入った皿を4つくらい並べ、「好み偏り過ぎだし!アハハ!」なんて大笑いする方が、絶対盛り上がるし、楽しいだろうと思ったからだ。
せっかくホームな空気感のあるフォルクスを選んだのに、ミユキは結局、アウェイで戦っているような孤独を感じてしまうのだった。
ところが…。
帰り道、夜風に吹かれながら、涼平はミユキの目をチラッと見つつ、恥ずかしそうにこんな告白をした。
「サラダバーにさ、コーヒーゼリーあったでしょ」
「あ、ありました、ありました!」
「俺さ、本当はあれ、3杯くらい食べたかったよ」
「えっ!?」
「でも、ミユキちゃんの手前、カッコつけちゃってさ。バカだよな、俺」
「フフ…ッ、後悔してるんですか?」
「めっちゃ後悔してる。でもミユキちゃんに嫌われたくなかったから…」
「そんなことで嫌うわけないじゃないですか」
「えーっ!?だって、ミユキちゃんすげー綺麗にサラダ盛り付けるし…」
「涼平さん!」
ミユキは、今までよりハキハキとした口調で、歯を見せてニッコリ笑うと、涼平にこんな提案をするのだった。
「今度、もう1回一緒にフォルクス行きましょ!その時は、お互い、本気で!本気でサラダバーと向き合いましょうよ」
ミユキは、自分の脳がアドレナリンで、半分緑色、半分黄色に染まっていくような不思議な感覚を味わっていた。










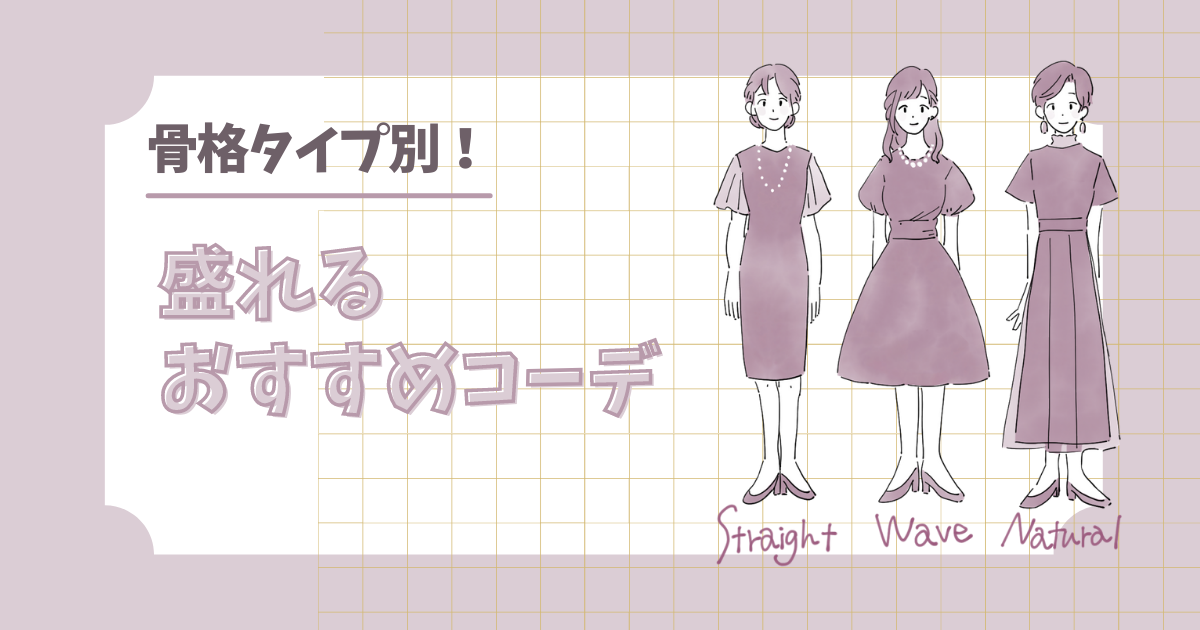







![.
💛夜職デビュー!ナイトワーク初心者向けの業界ガイド💛
ナイトワークをしてみたいけどよくわからない…という方に向けて、どういった風にナイトワークを探していけばいいか、わかりやすいガイドを書いてみました。初心者でわけもわからずになんとなくスマホでポチポチ~っと検索したら出てきたお店に入って「思ったのじゃなかった…」と失敗、なんて残念なことにならないように。まずは下準備をしてみることから始めましょう!
1️⃣ナイトワークの選び方!自分の働き方を見つけるには?
夜のお仕事というと札束!ドレス!スーツ!キラキラ輝く世界!かけひき!
…というイメージがありますが、まぁあながち間違ってはいません。それはさておき。まずは夜職選びの際に決めることは「本業」とするのか「副業・アルバイト」として働いていくのかで大きく変わってきます。
[ナイトワークを副業とする際の注意点]
まず本職が副業OKなのかどうかの確認が必須です。本業の少し足しにしたくて始めたのに、バレて本業がクビになってしまっては本末転倒!!それからたとえ副業がOKの会社だったとしても「ナイトワークで働く社員がいる」ということは、会社のイメージを損なうからという理由で本業にペナルティを追う場合もあります。
副業として行う場合、ナイトワークがバレないように気を付けるることにとにかく気を配ってください!地域を考慮することや、同僚や上司にバレにくい会員制の高級なお店にするなど、対策を考えておくことが大切です。
ただ、会員制のお店で社長とエンカウント!という可能性もあるので、バレにくい地域にするのが適策ですね。本職の会社からなるべく離れた地域をおすすめします。飲みに来た上司軍団に囲まれて逃げ場が無くなるなんてこともあり得ます。
自分の通える範囲でナイトワークがある地域、バレにくい穴場探しをしてみましょう。
[ナイトワークを本業とする際のお店探し]
ナイトワーク一本で働いていく場合、自分に合っている仕事がどういったものなのかやどれくらい月に稼げるかをしっかりと調べる必要があります。時間帯なども、生活リズムを変えていけるのか、日中働いていきたいのか。そういったことにも注目してみてください。
ナイトワークと一言で言っても細かく色々なジャンルがあります。
◯水商売
キャバクラ、クラブ、ガールズバー、ラウンジ、コンパニオンなど
◯風俗
デリバリーヘルス、ソープ、性感エステなど
◯その他ナイトワーク
メンズエステ、チャットレディなど。
男性も同じです!男性のナイトワークと言えばホストが有名ですがメンズバー、メンズパブ、女性用風俗など色々な働き方法がありますよ!
まずはこの大きなジャンルの中から自分が働いてみたいジャンルは何か決めましょう。
[体験入店をうまく利用しよう!]
ナイトワークでは通称「体入」という一日体験入店が出来るお店がほとんどです。お店によっては何度か体入できるお店も。
自分がどういう仕事が合ってるのかわからない場合、色々なジャンルのお店で一日体験として働いて決めてみるといいでしょう。もちろん、体験入店だけでもお給料はしっかりもらえるので安心してくださいね!
ナイトワークの体入はお店の求人サイトや、直接電話やLINEなどをして決めることが出来ます。「人が足りてないから今日すぐに来て!!」と言われることも珍しくないので、心の準備をしておきましょう。
2️⃣ナイトワーク業界はジャンル選びと体験が大切
ナイトワークと一言で言ってもたくさんのジャンルがあり、そのジャンルの中でも多くのお店があるので、自分に合ったものは何か、働きやすい場所を探してみると失敗が少ないです。また、週にどれくらい働きたいのか?どれくらいの稼ぎを目指すのかでも選ぶお仕事は変わっていきます。
そして自分の生活スタイルに合わせた働き方をすることも大切です。例えば、朝型の人が深夜まで働くことが難しい場合は、早めに閉店するスナックなどが適しているかもしれません。風俗などは日中働けるお店も多いほか、水商売では朝・昼キャバなどもあります。もともと朝に弱い方は逆に朝方まで営業しているお店がしっくりくる場合も。
ナイトワークはお客様と接することが多いため、人とのコミュニケーションが苦手な方は少しハードルが高いかもしれません。しかし、接客スキルを身につけることで、自信を持って仕事に取り組めるようになるでしょう。まずはなんでも体験!
自分に合ったお店で、輝いて働いてみてくださいね。](https://w-terrace.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)