ミユキと公輔は手を繋ぎ、仲良くマンガミュージアムの階段を降りると、そのまま近くの和食料理店、『えいたろう屋』へ向かった。
「その店って、ここから歩いてすぐなんでしょ?」
公輔が尋ねると、ミユキは「そうだよん」と軽快に答えた。
数年前、たまたま地元の先輩に連れていってもらった時、「道明寺蒸し」の美味さに衝撃を受けて以来。自分で予約をしてお客さんとえいたろう屋へ行くのは初めてのことだ。
「お刺身も美味しいし、何もかもが絶品だから、どうしても一緒に行きたくてさ」
「へー!ありがとう。そんな店、紹介してもらえて嬉しいわ」

関連ランキング:京料理 | 烏丸御池駅、丸太町駅(京都市営)、二条城前駅
店に到着すると、開店したばかりの店内にはまだ客がおらず、8席程あるカウンターの隅っこに2人並んで腰掛ける。
「めちゃくちゃいい感じの店じゃん」
「でしょ?」
「メニューがいい感じだよね。黒板に書いてある文字の書体がなんとも言えないわ」
「ふふっ、だよねだよね〜。ね、ハム輔、何飲む?」
ミユキは、公輔のことをハム輔と呼んでいた。漢字で書くと「公」は「ハム」と読めるからだ。
2人は年齢が一周りほど違っていたが、少年のようにピュアな感性を持つ公輔とミユキは波長が合っていて、同伴デートの時はいつも子供っぽい遊びを楽しんでは、キラキラとはしゃぎ、笑い合っていた。
「カンパーイ!」
ビールのグラスを軽く鳴らした後、ミユキはマンガミュージアムで公輔と楽しんだ「ぬりえ」の完成品をバッグから取り出し、眺めた。
「ぬりえ楽しかった〜!」
「俺も、ぬりえは何十年ぶりとかだったから、めっちゃ刺激になったわ」
「たまにはこういうデートもいいよね。ってか、ハム輔超センスあるね」
「ほんと?ミユキちゃんに褒められるとスゲー自信つくんだけど」
「センス超あるよ!ここのグラデーションとかハンパないじゃん」
2人は、同じキャラクターの絵に着色をしたのだが、カラフルに様々な色を使ったミユキと対照的に、公輔は統一感のある数色だけを使いこなし、色の濃淡を駆使して、プロのようなレベルの作品を仕上げていた。
「お造り盛り合わせでーす、お待たせしましたー!」
2人の席に運ばれて来たのは、氷や笹の葉の敷き詰められた美しい器。
そこに旬な魚や貝の刺し身が、芸術作品のように盛り付けられている。
「すっごーーーい!!!めちゃくちゃ映えるやつじゃん、これ!」
鯛や鮪が盛られている手前に、白くフワフワッとした刺し身があるのを見つけると、ミユキはさらにテンションを上げた。
「ねぇ、ハム輔、これハモじゃない!?」
「ウソ、マジ!?」
「ハモだよ絶対!だって身がフワフワしてるもん」
「俺、ハモめっちゃ好きなんだけど!今年初だよ」
「じゃあ、もう2人せーのでハモっちゃう?」
「ハモろう、ハモろう!」
口の中で、弾力のある身がフワッとほどけ、舌を包み込むように広がったのを感じると、ミユキは箸を置き、思わずワントーン高めの声で叫んでしまうのだった。
「なにこれ!ハモーい!」
「あはは、エモいみたいに言うなよ」
「こんなハモいもの食べたことないってマジで」
公輔の袖を掴み、ミユキは宙を仰ぎながら刺し身の旨さにジタバタと悶絶する。
そんなミユキの頭をポンポンと撫でてやる公輔。
2人は、完全に自分達だけの世界に浸り、笑い合っていたのだが…。
「あの〜…、それ、一応アナゴなんですよ〜」
カウンター越しに、料理長が申し訳なさそうにそう言った瞬間、ミユキも公輔も「ブッ…!」と、飲みかけのアナゴを氷の上に吹き出してしまいそうになった。
「いや〜、美味かったね!酒も魚も、道明寺蒸しも、最高だったよ、ミユキちゃん」
「ハモもっ?」
「いや、あれはアナゴだから」
「キャハハ!つーか、超恥ずかしかったんだけど!あれ全部聞かれてたんだね」
「俺らがあまりにもハモハモはしゃぐから、なかなか言い出せなかったのかな」
「また来ようね、ハモ輔〜」
「誰がハモ輔だ!」
一周り歳の離れた2人は、絶妙なハーモニーを奏でながら、夜の街へと消えていくのだった。









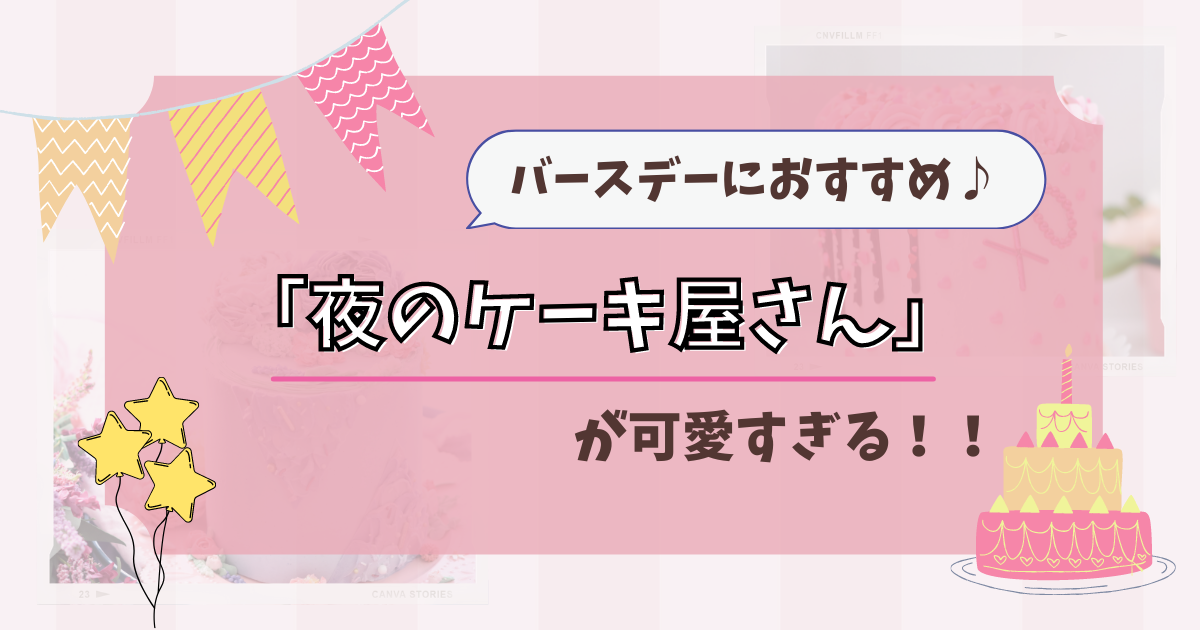
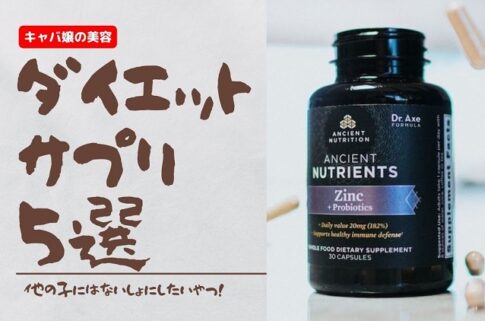
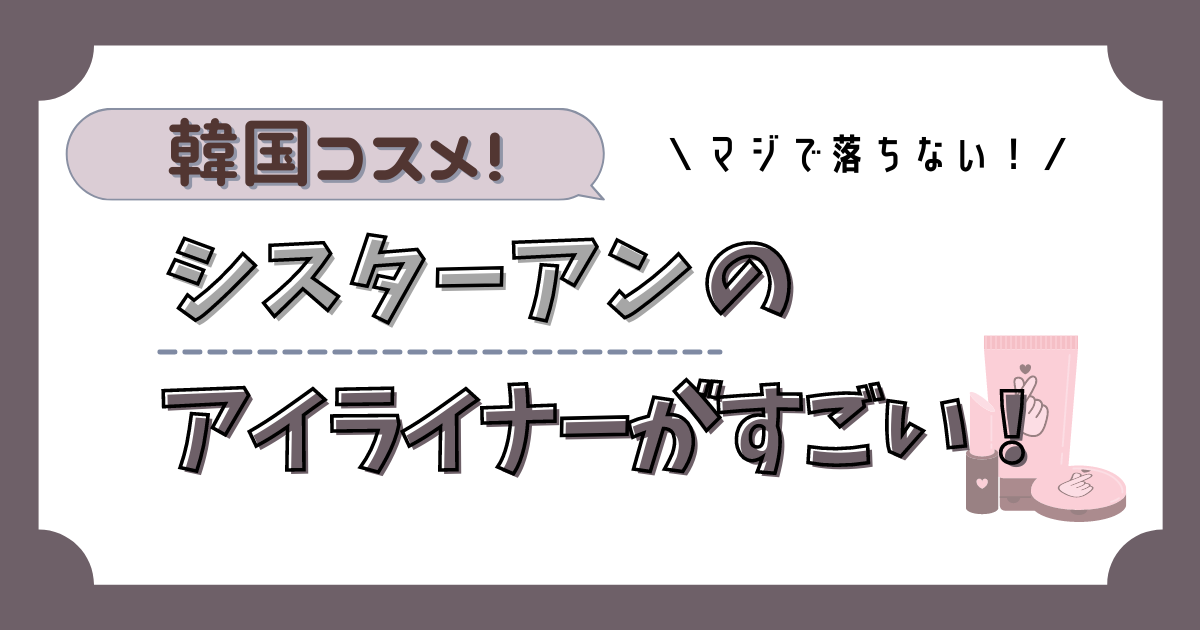






![.
💛夜職デビュー!ナイトワーク初心者向けの業界ガイド💛
ナイトワークをしてみたいけどよくわからない…という方に向けて、どういった風にナイトワークを探していけばいいか、わかりやすいガイドを書いてみました。初心者でわけもわからずになんとなくスマホでポチポチ~っと検索したら出てきたお店に入って「思ったのじゃなかった…」と失敗、なんて残念なことにならないように。まずは下準備をしてみることから始めましょう!
1️⃣ナイトワークの選び方!自分の働き方を見つけるには?
夜のお仕事というと札束!ドレス!スーツ!キラキラ輝く世界!かけひき!
…というイメージがありますが、まぁあながち間違ってはいません。それはさておき。まずは夜職選びの際に決めることは「本業」とするのか「副業・アルバイト」として働いていくのかで大きく変わってきます。
[ナイトワークを副業とする際の注意点]
まず本職が副業OKなのかどうかの確認が必須です。本業の少し足しにしたくて始めたのに、バレて本業がクビになってしまっては本末転倒!!それからたとえ副業がOKの会社だったとしても「ナイトワークで働く社員がいる」ということは、会社のイメージを損なうからという理由で本業にペナルティを追う場合もあります。
副業として行う場合、ナイトワークがバレないように気を付けるることにとにかく気を配ってください!地域を考慮することや、同僚や上司にバレにくい会員制の高級なお店にするなど、対策を考えておくことが大切です。
ただ、会員制のお店で社長とエンカウント!という可能性もあるので、バレにくい地域にするのが適策ですね。本職の会社からなるべく離れた地域をおすすめします。飲みに来た上司軍団に囲まれて逃げ場が無くなるなんてこともあり得ます。
自分の通える範囲でナイトワークがある地域、バレにくい穴場探しをしてみましょう。
[ナイトワークを本業とする際のお店探し]
ナイトワーク一本で働いていく場合、自分に合っている仕事がどういったものなのかやどれくらい月に稼げるかをしっかりと調べる必要があります。時間帯なども、生活リズムを変えていけるのか、日中働いていきたいのか。そういったことにも注目してみてください。
ナイトワークと一言で言っても細かく色々なジャンルがあります。
◯水商売
キャバクラ、クラブ、ガールズバー、ラウンジ、コンパニオンなど
◯風俗
デリバリーヘルス、ソープ、性感エステなど
◯その他ナイトワーク
メンズエステ、チャットレディなど。
男性も同じです!男性のナイトワークと言えばホストが有名ですがメンズバー、メンズパブ、女性用風俗など色々な働き方法がありますよ!
まずはこの大きなジャンルの中から自分が働いてみたいジャンルは何か決めましょう。
[体験入店をうまく利用しよう!]
ナイトワークでは通称「体入」という一日体験入店が出来るお店がほとんどです。お店によっては何度か体入できるお店も。
自分がどういう仕事が合ってるのかわからない場合、色々なジャンルのお店で一日体験として働いて決めてみるといいでしょう。もちろん、体験入店だけでもお給料はしっかりもらえるので安心してくださいね!
ナイトワークの体入はお店の求人サイトや、直接電話やLINEなどをして決めることが出来ます。「人が足りてないから今日すぐに来て!!」と言われることも珍しくないので、心の準備をしておきましょう。
2️⃣ナイトワーク業界はジャンル選びと体験が大切
ナイトワークと一言で言ってもたくさんのジャンルがあり、そのジャンルの中でも多くのお店があるので、自分に合ったものは何か、働きやすい場所を探してみると失敗が少ないです。また、週にどれくらい働きたいのか?どれくらいの稼ぎを目指すのかでも選ぶお仕事は変わっていきます。
そして自分の生活スタイルに合わせた働き方をすることも大切です。例えば、朝型の人が深夜まで働くことが難しい場合は、早めに閉店するスナックなどが適しているかもしれません。風俗などは日中働けるお店も多いほか、水商売では朝・昼キャバなどもあります。もともと朝に弱い方は逆に朝方まで営業しているお店がしっくりくる場合も。
ナイトワークはお客様と接することが多いため、人とのコミュニケーションが苦手な方は少しハードルが高いかもしれません。しかし、接客スキルを身につけることで、自信を持って仕事に取り組めるようになるでしょう。まずはなんでも体験!
自分に合ったお店で、輝いて働いてみてくださいね。](https://w-terrace.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)